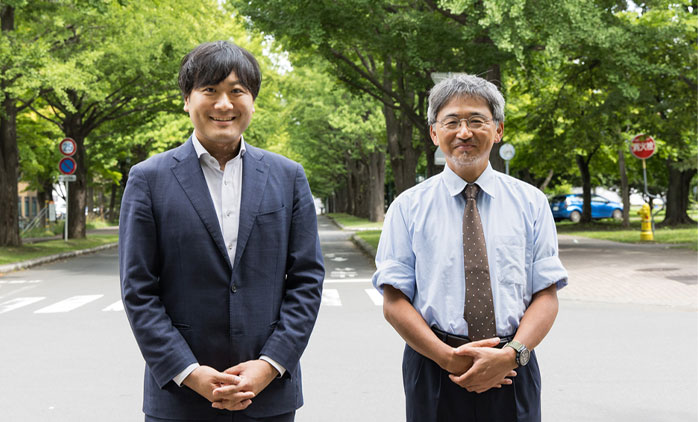未来テクノロジー
テクノロジーが拓く、豊かな未来。挑戦し続ける人と企業をクローズアップ

須田 信也さん
株式会社WordLink & Company 代表取締役社長
1979年京都府生まれ。高校卒業後、渡米。アリゾナ州立大学在学中に日本食材のデリバリーサービスを起業。同事業を売却後、帰国。2008年からローム株式会社の欧米営業本部で海外営業を担当。2014年8月に独立し、株式会社WorldLink & Companyを設立。2024年10月にEXEDYグループに参画、現在に至る。
福島イノベーション・コースト構想から、日本初となる本格的なドローンの販売、メンテナンス、運用支援を含む総合サービスが誕生した。「SkyLink Japan」というブランド名で、ドローンと社会の新しい関係性を創造するWorldLink & Company。同社代表取締役社長の須田信也氏に、事業構想の原点からサービスの現状、そして福島から全国へと広がる新たなビジネスモデルの可能性まで話を聞いた。
─どのような経緯でドローンビジネスに着目されたのでしょうか。
須田:
2014年8月、半導体製造装置メーカーを退職後、仲間と2人でWorldLink & Companyを設立しました。当初は社名の通り、世界中のさまざまな製品を扱いながら、グローバルにつながる企業を目指していました。
私自身が海外のガジェットに興味があったので、日本ではまだ販売されていないカメラや玩具の輸入販売などを手がけていました。その過程でドローンと出会い、並行輸入の可能性を探り始めたのです。
当時からドローン市場は中国メーカーが圧倒的なシェアを持っていました。2015年1月、中国の大手ドローンメーカーと正規代理店契約の交渉を始めたところ、「まず1000万円分の製品購入」という条件が示されました。友人たちからお金を借り入れて仕入れたところ、予想以上の速さで完売しました。
折しも首相官邸へのドローン落下事件が発生し、ドローンへの社会的な認知度が一気に高まりました。この追い風を受け、販売事業は急速に成長。「SkyLink Japan」というブランドを立ち上げ、京都・北山に実店舗をオープンし、販売だけでなく使用方法の指導やサポートまで行うビジネスモデルを確立しました。
マルチベンダー化とBtoBビジネスの深化を目指して福島へ
─京都で創業された会社が、なぜ福島でビジネスを展開することになったのでしょうか。
須田:
実店舗展開の背景には、前職の半導体製造装置メーカーでの経験も生きています。単なる製品販売で終わるのではなく、サポートまで含めた本格的なBtoBビジネスを実現したいという思いがありました。そこで店舗を情報発信の拠点とし、実証実験の請負まで手がけるようになりました。
転機となったのは2021年です。ドローン事業は順調でしたが、中国の大手ドローンメーカー1社への依存度が9割を超える状況にビジネスリスクを感じていました。そこで国産ドローンメーカー合弁会社設立時に出資を決断してマルチベンダー化を進めたところ、中国のメーカーとの関係が悪化し、売上が減少する事態となりました。
しかし、マルチベンダー戦略とBtoBビジネスへのこだわりは揺るぎませんでした。修理やメンテナンスなどの総合サポート拠点を模索する中で、福島との出会いがありました。
当初は北海道や九州も候補地として検討していました。特に北海道は、土地・物件価格の優位性に加え、急成長する農業用ドローン市場の将来性を見据えての選択でした。しかし、実地調査を進めると、本州からの距離がサポートビジネスのコスト面で大きな課題となりました。
その頃、福島イノベーション・コースト構想推進機構(以下、福島イノベ機構)でロボットとドローンが重点分野に位置づけられていることを知りました。実は2011年の東日本大震災当時、半導体製造装置メーカーで海外顧客を担当していた私は、被災した宮城工場の部品調達問題に直面し、個人として無力さを痛感した経験があります。その思いも重なり、福島での事業展開を決意しました。
進出先は、富岡町や浪江町も検討しましたが、ご縁あって双葉町に決定しました。当社の顧問が双葉町長と面識があり、その紹介で町長にお会いする機会を得ました。私どもの構想にご賛同いただき、企業立地協定の締結に至ったのです。
 中国メーカー1社への依存から脱却し、マルチベンダー化を進めることで、より充実したBtoBサービスの展開を目指す。その拠点として選んだのが福島だった
中国メーカー1社への依存から脱却し、マルチベンダー化を進めることで、より充実したBtoBサービスの展開を目指す。その拠点として選んだのが福島だった
ドローンの安定稼働を支えるメンテナンス・保管の総合サービスを確立
─現在、どのようなビジネスを展開されているのでしょうか。
須田:
現在の主力事業は、ドローンのメンテナンスと保管サービスです。2021年にパーツセンター業務を行う「福島浪江サービスセンター」を開設し、2024年1月には双葉町に「SkyLink Hangar福島」をオープンしました。これは、ドローンのメンテナンスと保管に特化した総合サービス施設です。
ドローンの運用において、バッテリー管理は重要な課題となっています。定期的な充放電を怠ると過放電状態となり、機体が使用できなくなるリスクがあります。同様に、ファームウェアの定期的なアップデートも不可欠です。これらのメンテナンスが適切に行われないと、いざという時にドローンが起動できないという事態に陥りかねません。
特に自治体では、災害対策用のドローンが長期間倉庫に保管されたまま、適切なメンテナンスが行われていないケースが少なくありません。そこで私たちは、使用頻度が下がる時期に機体をお預かりし、総合的なメンテナンスを行うサービスの構築を目指しました。例えば、農業用途の場合は冬場、産業用途の場合は春から初夏に使用頻度が低くなるため、これらの時期をメンテナンス期間として活用しています。
現在、当社の施設では多数のドローンをお預かりし、定期的な充放電管理やファームウェアのアップデートを実施しています。使用時期に合わせて発送し、使用後は再び受け入れてメンテナンスを行う。このドローンを常に安心して使える状態に保つ循環型のサービスモデルを、ここ福島で確立することができました。
 2024年1月に開設したSkyLink Hangar福島。約4,060坪の敷地内には、工場兼倉庫棟、バッテリー保管庫、フライト場を備え、ドローンの総合メンテナンス拠点として機能している
2024年1月に開設したSkyLink Hangar福島。約4,060坪の敷地内には、工場兼倉庫棟、バッテリー保管庫、フライト場を備え、ドローンの総合メンテナンス拠点として機能している
(写真提供:WordLink & Company)
─サポート提供における技術的な課題についてお聞かせください。
須田:
最も重視しているのが温度・湿度管理です。冬場の低温はバッテリーの放電を促進しますし、この沿岸部特有の塩害も機器への負担となります。そのため、エアコンの設置や特殊換気システムの導入など、倉庫内を常に最適環境に保つための設備投資を行っています。
ただし、保守・メンテナンス自体は特別な専門性を必要とするものではありません。基本的なパソコン操作ができ、機械に興味がある人材であれば、必要な電気系の知識やスキルは社内で育成できます。福島市内や浜通り地域からの雇用も確保しています。
─事業展開を通じて見えてきた課題は何でしょうか。
須田:
最大の課題は法規制の問題ですね。例えば、2024年2月に富岡町で実施したドローンによる夜間スカイパトロールの実証実験では、当初目指していた完全自動運転が規制の壁に直面しました。物流分野でも同様の課題があります。第三者上空の飛行が制限されていますから、効率的な物流網の構築が難しい状況です。
人口密度が比較的低い福島でも、鉄道や高速道路上空の飛行には厳しい制限があります。浜通り地域をモデルケースとして、規制緩和と実証実験の機会を広げていただければと考えています。
現行法では、ドローンは「無人航空機」として位置づけられており、申請・許可手続きの複雑さやコスト負担が事業展開の障壁になっています。より柔軟な活用を可能にする制度設計への期待は大きいですね。
─ドローン市場の現状と展望はどのようにお考えですか。
須田:
サービス市場は規制緩和次第で大きな成長が期待できます。ただし、現状では市場の8割を中国の大手メーカーが占めているという課題があります。国産メーカーも台頭していますが、価格競争力の面で苦戦が続いています。関税政策などの支援がなければ、量産体制の確立は難しいでしょう。
また、国産ドローンの開発が停滞するもう一つの要因として、ドローンの軍事利用に対するイメージがあります。ウクライナ戦争でもドローンの活用が注目されましたが、こうした側面が日本の大手企業の参入を躊躇させている可能性があると感じています。日本企業には、軍事関連産業を毛嫌いする傾向が根強くあり、その結果として、ドローンの開発に大きな予算を割くことを避けるケースが多いように思います。このような姿勢が、国産ドローンの競争力向上を阻む一因になっていると考えています。
─具体的なドローンの活用分野についてお聞かせください。
須田:
現在の主力分野は、農業、測量、そして点検です。まず、農業分野では、農薬散布や作物の生育状況のモニタリングなどでドローンの利活用が進んでいます。特に広大な農地を抱える地域では、その効率性から利用が急速に拡大しています。また、ドローンによる散布面積は年々増えているため、効率的な散布サービスも活性化しています。
次に、測量分野では、すでに多くの場面でドローンによる写真撮影やLiDAR(レーザー測量機器)による計測が活発に利用されています。しかし、市場の拡大に伴い外注先が不足しているという課題があり、特に高精度な測量には高額なLiDAR機器が必要となるため、個別案件では採算が取りにくい状況です。この課題に対して、当社では機材とパイロットをパッケージで提供する事業モデルを構築し、全国規模のパイロットネットワークを整備することで対応を進めています。
最後に、点検分野です。特に電力会社では、これまでヘリコプターで行っていた定期点検業務をドローンに段階的に移行する動きが加速しています。ドローンはより安全かつ低コストで点検を行うことが可能で、特にインフラ老朽化が進む中でそのニーズが高まっています。この分野で成功する鍵は、いかにお客さまに効率的かつ迅速なサポートサービスを提供できるかにあると考えています。

 ドローンの活用領域は測量、物流、農薬散布、インフラ点検へと広がりを見せる。
ドローンの活用領域は測量、物流、農薬散布、インフラ点検へと広がりを見せる。
特に電力会社では、従来のヘリコプターによる点検作業からドローンへの移行が進む
(写真提供:WorldLink & Company)
福島イノベ機構との連携を基盤に新規事業の創出へ
─福島イノベ機構は御社にとってどのような存在でしょうか。
須田:
2021年に初めて拠点を構えた南相馬市産業創造センターから現在に至るまで、福島イノベ機構は地域との絆を築く上で不可欠なパートナーです。イベントの開催支援や、自治体・地元企業とのマッチングなど、多岐にわたるサポートをいただいています。
物流網の構築や人材採用でも、機構の支援は大きな力になっています。現在の双葉町での事業展開も、用地確保から建物建設の補助金まで、全面的なバックアップがあってこそ実現できました。
補助金の条件であった雇用創出は、むしろ想定以上の成果を上げています。事業拡大に伴う人員増加で、現在の施設では手狭になってきているほどです。収益面でも黒字化を達成し、さらなる事業拡大を視野に入れています。
今後は営業人材を強化し、自治体向けの新規事業提案や地元建設コンサルタント会社との測量事業協業など、収益モデルの多様化を図っていきます。
さらに、本年は国産ドローンの製造にも着手する計画です。初期ロットとして20~30台を生産し、地元企業向けに展開することを検討しています。購入額の半額が補助金でカバーされる制度を活用することで、福島発の地産地消モデルを確立できると考えています。
この拠点を「マザー工場」として位置づけ、市場拡大とともに福島発のドローンビジネスモデルを全国展開することが私の描く将来像です。各地域にメンテナンス拠点を設けることで、より迅速かつ低コストなサービス提供が可能になります。
さらに、民間初のドローン車検工場の実現も目指しています。低価格な車検システムの確立と規制緩和が進むことで、ドローンの社会実装がさらに加速し、活用領域も大きく広がっていくはずです。
 「福島イノベ機構のサポートを得て、自社製ドローン製造や民間初のドローン車検工場の実現を目指す」と語る須田氏
「福島イノベ機構のサポートを得て、自社製ドローン製造や民間初のドローン車検工場の実現を目指す」と語る須田氏
─最後に、福島での起業を目指す方々へのメッセージをお願いします。
須田:
もし弊社のようなロボット関連などで起業を目指されている方でしたら、まずは福島イノベ機構への相談をお勧めします。福島での事業展開における重要なハブとして、さまざまな支援を提供してくれます。ドローンやロボットの分野において、人口密度が比較的低い福島は実証実験の最適なフィールドとなっています。
この広大な土地で安全性の実証実績を積み重ねることは、他地域での事業展開においても大きな説得力を持ちます。当社も、京都では実現が難しい実証実験をここで実施しています。浜通り地域は、新技術の検証拠点として、また使い勝手の良い産業団地として、大きな可能性を秘めています。未来を見据えた挑戦の地として、この福島の地でぜひ皆さんの夢を実現してください。
株式会社WordLink & Company
2014年8月設立。ドローンの総合サービスを提供する企業として、「SkyLink Japan」ブランドを展開。販売、メンテナンス、保管、運用支援を主軸に、農業、測量分野での活用を推進。特に福島県双葉町に「SkyLink Hangar福島」を開設し、ドローンの社会実装に向けた新たなビジネスモデルの創出を目指す。京都に本社を置きながら、福島を主要拠点として全国展開を図り、ドローンを活用した地域課題の解決に取り組んでいる。
福島イノベーション・コースト構想推進機構による支援:
・令和3、4年度「Fukushima Tech Create」ビジネスアイデア事業化プログラム採択(事業名:ドローンのメンテナンス及び保管サービス、ドローン総合管理サービス)