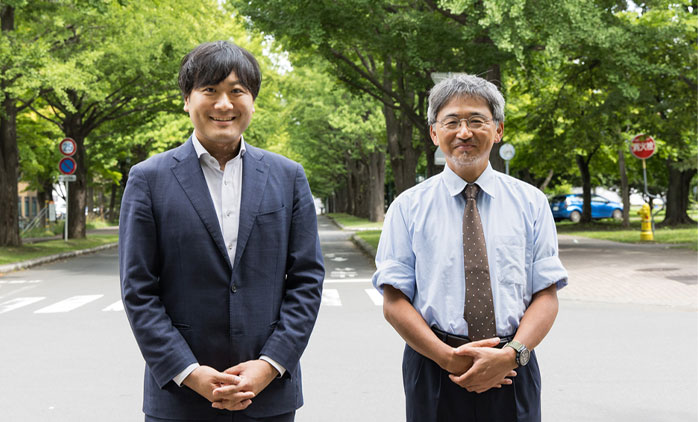TOPICS
世界に類を見ない「陸・海・空のフィールドロボット」一大開発実証拠点として、福島ロボットテストフィールド(以下、RTF)が福島県浜通り地域等(※)の新産業創出を牽引している。公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構(以下、福島イノベ機構)が運営するRTFは、開所以来、1100件を超える敷地内実証実験が行われた。東日本大震災以降、同地域にはすでにロボット関連企業81社が進出し、その一部となる5社が2025年1月21日、東京都内で最新の研究開発成果を発表した。
※福島県浜通り地域等:福島県いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村の15市町村
福島イノベ機構は1月21日、東京・品川でメディア発表会を開催した。冒頭、復興庁の牛尾則文審議官がRTFと同機構への期待を述べた。続いて同機構の蘆田和也事務局長が登壇し、福島イノベーション・コースト構想の概要とともに、復興は道半ばながら着実に進出企業が増えていることを報告。その後、RTFの鈴木真二所長(東京大学名誉教授)が施設の歩みと取り組みについて説明を行った。
RTFを活用する企業5社による成果報告とトークセッションに続き、F-REI(福島国際研究教育機構)研究開発推進部の大今宏史部長が登壇。4月1日に予定されているRTFとF-REIの統合について説明し、新たな科学技術・産業の一大拠点を目指す今後の展望を示した。
国家戦略に位置づけられた
ロボット開発の実証拠点へ
東日本大震災で甚大な被害を受けた福島県浜通り地域等の産業復興を目指し、「福島イノベーション・コースト構想」が策定された。これは、浜通り地域等の産業復興と日本を牽引する新産業創出を目指す「福島復興再生計画」の一環として位置づけられた国家プロジェクトである。「廃炉」「ロボット・ドローン」「エネルギー・環境・リサイクル」「農林水産業」「医療関連」「航空宇宙」を重点6分野として、産業復興に取り組む。
「福島県はイノベ構想を推進する中核的な機関として、2017年に福島イノベ機構を設立し、①産業集積、②教育・人材育成、③交流人口の拡大、④拠点施設の管理運営、⑤情報発信等の事業に加え、『ふくしま12市町村移住支援センターの運営』を含めた6つを軸に振興策を推進しています」と蘆田事務局長は説明する。
イノベ構想の「ロボット・ドローン」分野における産業集積の核となっているのがRTFだ。その設立は、2015年に政府の日本経済再生本部が「ロボット新戦略」で示した災害対応ロボット等の実証実験場整備という課題に応えたものである。構想の第一歩として「福島浜通りロボット実証区域」が設置され、区域内のダム、校舎、産業廃棄物処分場、トンネルなどを活用し、水中作業ロボットやドローンの実証実験が実施された。これらの経験と知見を基にRTFの整備が進められ、2020年に全面開所を迎えた。
 福島ロボットテストフィールド(RTF)全景。南相馬市の約50ヘクタールの敷地に、水中・陸上・空中ロボットの研究開発・実証試験が可能な21の試験施設を整備。浪江町の施設と合わせ、世界に類を見ない一大開発実証拠点となっている
福島ロボットテストフィールド(RTF)全景。南相馬市の約50ヘクタールの敷地に、水中・陸上・空中ロボットの研究開発・実証試験が可能な21の試験施設を整備。浪江町の施設と合わせ、世界に類を見ない一大開発実証拠点となっている
南相馬と浪江に広がる
世界最大級の実験施設
「『陸・海・空のフィールドロボット』の開発実証拠点は世界にも類がなく、災害対応ロボットやドローン、次世代モビリティの開発に必要なさまざまな実験が可能です。自衛隊や消防の訓練にも対応しています」とRTFの鈴木所長は説明する。
全面開所から5年が経過したRTFだが、一部開所時のデータを含めた敷地内での実証件数は1121件(2017年9月~2024年12月)に達する。そのうちドローン関連が65%を占めている。
RTFは南相馬市と浪江町の2つのエリアに施設を展開している。南相馬市の復興工業団地内には、約50ヘクタールの敷地に陸海空で動くロボットやドローンの実証試験用設備を配置。研究者の活動拠点となる研究棟も整備されている。浪江町には無人航空機用の滑走路と格納庫を設置。さらに、南相馬市と浪江町を結ぶ無人機の広域飛行ルートの環境整備に努めている。
RTFの効果は、浜通り地域に81社のロボット関連企業が進出している実績からも明らかである。
ロボット関連企業81社が進出
代表5社が成果を報告
メディア発表会では、RTFを活用する5社が研究開発の成果を発表した。
 RTFを拠点に先端技術開発を進める5社の代表者。左から、クフウシヤ・大西威一郎氏、リビングロボット・川内康裕氏、人機一体・金岡博士、テトラ・アビエーション・中井佑氏、イームズロボティクス・曽谷英司氏
RTFを拠点に先端技術開発を進める5社の代表者。左から、クフウシヤ・大西威一郎氏、リビングロボット・川内康裕氏、人機一体・金岡博士、テトラ・アビエーション・中井佑氏、イームズロボティクス・曽谷英司氏
イームズロボティクスの曽谷英司氏は「ドローンで支える命と暮らしを守る物流インフラの構築」をテーマに発表。平時と災害時の物資輸送をドローンで担う実証実験について報告し、能登半島地震の災害支援で直面した通信障害や降雪、強風などの課題解決に取り組む方針を示した。
テトラ・アビエーションの中井佑氏は「シームレスな移動を実現する空飛ぶクルマのある未来」について発表。同社は、移動時間を重視するビジネスパーソンに向けた遠隔地アクセス用の空飛ぶクルマを開発中で、2025年大阪・関西万博への出展を予定している。米国市場では富裕層をターゲットとした展開を計画している。
人機一体の金岡博士は「あまねく世界からフィジカルな苦役を無用とする」というビジョンの下、重作業や高所作業に対応する双方向制御型の人型重機を紹介。すでにJR西日本では日本信号と協働し、多機能鉄道重機として実用化しており、その実績を基に災害対応ロボットの開発に取り組んでいる。
リビングロボットの川内康裕氏は「ロボットと人が共に生きる社会の実現」をビジョンとして掲げる。同社の小型パートナーロボット「あるくメカトロウィーゴ」は見守り介護や教育用途で注目を集めており、最近ではRTFを活用して「自動走行式草刈りロボット」を開発中である。
クフウシヤの大西威一郎氏は「イノベ地域の新しいチャレンジ」と題し自社事業を説明。ニッチ市場のニーズに着目し、大手企業が参入していない領域での自律移動ロボットの研究開発を推進している。その成果は、大阪・関西万博で予定されている視覚障がい者向けのスーツケース型のロボットの実証実験で披露される予定だ。
 RTFで開発が進む次世代製品群。左上から時計回りに、人機一体の人型重機、リビングロボットのプログラミング学習用ロボット、テトラ・アビエーションの空飛ぶクルマ、クフウシヤの自律移動ロボット、イームズロボティクスの物流ドローン
RTFで開発が進む次世代製品群。左上から時計回りに、人機一体の人型重機、リビングロボットのプログラミング学習用ロボット、テトラ・アビエーションの空飛ぶクルマ、クフウシヤの自律移動ロボット、イームズロボティクスの物流ドローン
研究開発力を結集し
世界水準の拠点形成へ
登壇した5社の多くが製品の設計・制御開発に強みを持つファブレス企業である。試作機の開発には製造現場の支援が不可欠だが、浜通り地域には大手メーカーの精密加工を請け負う優れた工場が多数存在する。
RTFを活用するファブレス企業は、実証環境と製造環境の両面で充実した基盤を得ている。さらに、RTFと研究機関であるF-REIの統合が決定し、新たな発展段階を迎えようとしている。
この統合により、RTFの機能と成果をF-REIが継承し、ロボット分野の研究開発、産業化、人材育成の一層の強化が見込まれる。さらには、2024年6月、福島県と長崎県は「新技術実装連携“絆”特区」として指定され、全国に先駆けてドローンによるオンデマンド配送の実現に取り組んでいる。
福島イノベ機構は統合後もRTFの運営を担い続ける。浜通り地域は、世界に向けて躍進するロボット・ドローン産業の一大集積拠点として、さらなる発展を目指している。
(本記事は「日経ビジネス」2025年3月17日号に広告記事として掲載されたもので、日経BPの許可を得て転載しています)
公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構
〒960-8043 福島県福島市中町1-19 中町ビル6階
https://www.fipo.or.jp/inquiry