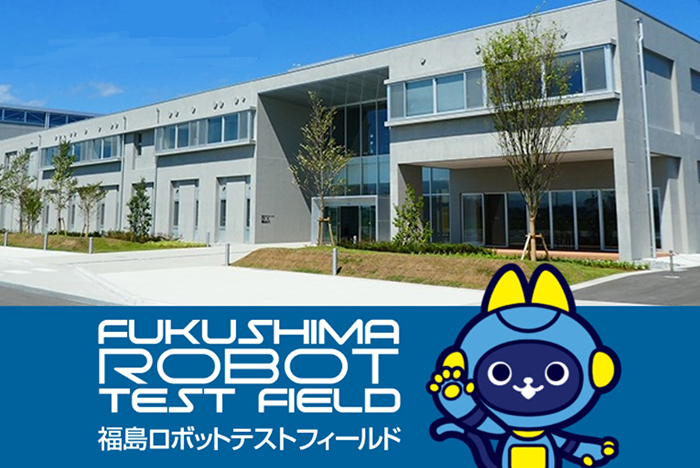恒栄電設株式会社
最近の企業参入例
恒栄電設株式会社
浪江町で「フラワーファームなみえ」を運営。電気設備のノウハウを活かして「トルコギキョウ」を栽培
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 社名 | 恒栄電設株式会社 |
|---|---|
| 業種 | 電気工事、農業用設備の製作・製造及び販売、農産物の生産・加工及び販売 |
| 代表 | 小林永治さん |
| 所在地 | 東京都北区 |
| 法人設立 | 1955年2月 |
| 従業員数 | 260名 |
| 資本金 | 5,280万円 |
| 生産科目 | トルコギキョウ |
小林永治さん プロフィール

1963年生まれ、日本大学芸術学部卒業。1991年恒栄電設株式会社へ入社、2014年に代表取締役社長に就任。
2020年から本格的に農業事業に参入し、浪江町に「フラワーファームなみえ」を建設。震災復興と持続可能なまちづくりを目指し、花卉栽培を行っている。電気工事で培った技術を活かし、地域エネルギーを地域生産に活用する「地産地活」モデルの普及を推進。地域と共に笑顔の絶えない未来を創る挑戦を続けている。
農業参入のきっかけについて

恒栄電設の創業者は福島県の浜通り(南相馬市)出身で、創業に関わるゆかり深い町でした。
そこで震災からの復興、持続可能なまちづくりに貢献したいという思いを強く抱き、この地で花卉栽培事業を始めました。
現在、農業に限らずあらゆる産業でIT化が浸透しており、電気技術は不可欠となっています。
花卉事業においては、栽培環境(温度、光合成に必要な二酸化炭素濃度、光量子、土中水分など)の自動コントロールに、恒栄電設の様々な技術が活かされています。
私たちは、電気設備業ですので再生可能エネルギーを浪江町に作りたいとの思いがありました。
その中で、作るだけでは「地産」はできるが「地活」にならない。地産地活型のエネルギーを考えた時に「何がエネルギーを有効に使えるか。」で花卉栽培をはじめました。
今後は、再生可能エネルギーで栽培した「トルコギキョウ」を多くの方に届けたいと思っています。
■ 12市町村における農業参入状況
| 参入場所 | 浪江町 |
|---|---|
| 参入年月 | 2020年 |
| 参入規模・栽培品目 | トルコギキョウ 0.1ha(1万5000株) |
恒栄電設(電気設備会社) 小林永治社長
「農業は夢のある仕事です。」
東京に本社を置く恒栄電設の小林永治社長は微笑みながら語った。
3年前トルコギキョウ栽培に新規参入したこの会社。


「農業は夢のある仕事です。」
東京に本社を置く恒栄電設の小林永治社長は微笑みながら語った。
3年前トルコギキョウ栽培に新規参入したこの会社。
フラワーファームなみえ


それが浪江町にある“フラワーファームなみえ”だ。
現在、2棟のハウスで約1万5千株のトルコギキョウを栽培している。
電気設備専門のノウハウを生かして考えたのは、環境モニタリング装置。
環境モニタリング装置
積算温度が「一定温度」になると開花するトルコギキョウの湿度や温度を管理し栽培に最適な状況をつくりだす。さらに驚くべきは操作が遠隔で可能になったことだ。


積算温度が「一定温度」になると開花するトルコギキョウの湿度や温度を管理し栽培に最適な状況をつくりだす。さらに驚くべきは操作が遠隔で可能になったことだ。
ポリエステル培地を使った水耕栽培


しかし、はじめから順風満帆だったわけではなく、試行錯誤を重ねた結果たどり着いたのが、サブスク用の花だった。
この定期的に切り花が届くサービスに着目すると業績があがったという。


ここで栽培されているトルコギキョウは、家で飾ることを前提にしているので草丈が短く一つ一つの花も株もコンパクト、収穫量があがり経営も安定していった。


そして新たな取り組みも始めた。ポリエステルを使っての水耕栽培だ。ポリエステルの作業服を使って開発した培地によって生育環境が制御しやすくなった。また立った姿勢で作業が可能になり、高齢者や障がい者でも働くことができるようになった。
花卉の一大産地化を目指す浪江町
これが、小林社長が目指す農業の未来。
「誰もが農業に従事しやすくなり、農業人口を増やしたい。」
それは、東日本大震災から新しいまちづくりを目指す浪江町にとっても「花卉の一大産地化」に向けて大きな力となる。

これが、小林社長が目指す農業の未来。
「誰もが農業に従事しやくすなり、農業人口を増やしたい。」
それは、東日本大震災から新しいまちづくりを目指す浪江町にとっても「花卉の一大産地化」に向けて大きな力となる。